大山です、
「今の給料じゃちょっとキツいな…」
「スキマ時間に副業して、少しでも収入を増やしたい」
そう思ってる公務員の方も多いと思います。
でも……
「バレたらヤバいんじゃないの?」
「そもそも副業って禁止じゃなかったっけ?」
そんな不安もあるはずです。
でも実は、公務員でも
副業がまったくできないわけじゃありません。
ルールさえ守れば、
ちゃんと副業で収入を得ることはできます。
月に数万円、年間で数十万円の副収入も夢じゃない。
この記事では、
・どんな副業ができるのか?
・何に気をつければいいのか?
・やってはいけない副業とは?
ということを、
しっかり解説していきます。
もしルールを無視して副業をやってしまうと、
懲戒処分になることもあります。
実際に処分された事例もあるので、
それも踏まえながら
しっかりお伝えしていきます。
ぜひ最後までお読みください。
そして現在、弊社では
無料オープンキャンパスを開講しています。

無料オープンキャンパスでは
・マーケティング
・コピーライティング
・プロモーション
3つの本質スキルを学べ
ビジネス社会に求められる新職種
セールスプロモーターの全貌を明かしています。
完全在宅で仕事をしていきたい
低単価から脱却し、高単価の仕事をしたい
誰かの役に立つビジネスをしたい
そう考える方は、
今すぐに下記リンクから
無料オープンキャンパスにご参加ください。
https://ug.zeroichi-01.com/p/Yn3YoHq40uxE?ftid=dHCkHHe9ZbZm
公務員の副業ルール
まず最初に知ってほしいのは、
「公務員の副業は全面的にダメ」
というわけじゃないということです。
条件つきではありますが、
ちゃんと副業ができるルールになっています。
「え?なんで一部はOKで、一部はダメなの?」
その理由は、じつは“憲法”にあります。
憲法では、すべての国民に
「仕事を選ぶ自由」や「お金や財産をもつ権利」
があると決められています。
この自由や権利は、
公務員にも当然あるものです。
ただし、ここで鍵になるのが
「公共の福祉に反しないかどうか」という考え方です。
「公共の福祉」って
ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、
簡単に言えば
「みんなの利益や安心を守るために必要な制限」のこと。
だから、法律で副業を
全部ダメというふうに言い切ることはできないけども、
「公共の福祉」に反する副業はNGだよってことになります。
じゃあ具体的に、何が“反する”のか?
次のパートでは
「公共の福祉」の考え方をもとに、
どんな副業がアウトなのかを
4つのポイントにわけて解説していきます。
公共の福祉:4つの大事なルール
ルール1: 公平中立であること
公務員は、誰に対しても
平等であることが求められます。
たとえば、市役所の人が
副業でレストランをやっていたとします。
その人が食品衛生の検査をする立場だったら、
自分の店に甘く、ライバルの店に厳しくするかもしれないですよね?
それって、明らかに不公平です。
公務員がそんなことをすれば、
市民からの信頼は一気になくなります。
だからこそ、仕事では
中立であることが絶対に必要なんです。
ルール2: 汚職を防ぐため
副業の内容が、
本業と関係していると危ないです。
たとえば、
市役所で建築の許可を出す仕事をしている人が、
建設会社で副業していたら……
「この申請、早く通してあげるからさ、
給料ちょっと多めにくれない?」
なんて話になったら、完全にアウトです。
こういうズルが起きないように、
最初からそういう副業は
禁止にしておく必要があるんですね。
ルール3:情報を守ること
公務員は、住民の個人情報や、
役所の中の情報など、大切な情報をいっぱい扱っています。
だから、副業をしてるときに
「うっかり言っちゃった!」じゃすみません。
情報の取り扱いは、
本当に慎重じゃないとダメなんです。
ルール4: 本業にちゃんと向き合うこと
副業ばっかりに力を入れて、
夜遅くまで働いて寝不足。
次の日、仕事中にミスが連発する。
そんな状態で、
「税金から給料をもらってる人」が
ちゃんと働いてないってなると、大問題です。
公務員はまず、
本業にしっかり取り組むことが大前提。
副業のせいで
本業がおろそかになるのは、絶対にNGです。
この4つをちゃんと守っていれば、
公務員だって副業をしていいんです。
では実際に、法律ではどう書かれているのか?
国家公務員と地方公務員で、
それぞれ少し違うので、確認していきましょう。
法律での決まり
国家公務員の場合
国家公務員法の中に、こんなルールがあります。
● 第103条
会社経営及び会社役員就任は不可
● 第104条
許可なく副業をすることは不可
つまり、許可がないと
副業も会社経営もできないということです。
地方公務員の場合
地方公務員法で、こう書かれています。
● 第38条
任命権者(あなたを採用した人や部署)からの許可無しに
会社役員就任、会社経営等は不可。
これらは、すべてダメです。
まとめると、
国家公務員も、地方公務員も
「許可をちゃんと取れば副業できる」ということです。
ここで注意したいのが、
“継続的な収入”があるかどうか。
一回きりの仕事なら
許可がいらないケースもありますが、
続けて収入が入る副業なら、
必ず許可を取りましょう。
公務員にもできる副業
副業のルールがわかったところで、
ここからは
「じゃあ実際にどんな副業ならできるのか?」
を、見ていきましょう。
公務員でも取り組みやすい副業を、
8つ紹介していきます。
公務員にもできる副業1: 不動産投資
これは定番中の定番ですね。
不動産投資は
安定収入を得られる可能性があるので、
公務員の方に人気の副業です。
なぜかというと、
公務員は「収入が安定している」から、
銀行からのローン審査が通りやすいんです。
ただし、やっていい範囲にはルールがあります。
・家やアパートは、建物5棟まで・部屋数10室まで
・土地の賃貸は10か所まで
・駐車場は、機械を使わず10台まで
・1年間の家賃収入は500万円未満に抑える
これを超えると、
「商売」と見なされる可能性が出てきます。
とはいえ、年500万円の
家賃収入を得るには数年はかかります。
「500万超えたらどうしよう…」と悩むより、
まずはルール内で始めてみることが大事ですね。
公務員にもできる副業2: 株式・投資信託・FX・仮想通貨
いわゆる「資産運用」ですね。
これらは「働いて稼ぐ」副業ではなく、
お金に働いてもらう「投資」なので、
基本的には自由にできます。
ただし注意点もあります。
金融機関に出向している場合、
投資を自粛するように言われることがあります。
理由は、他人のお金を扱う立場にあるから。
また、勤務時間中の取引も禁止です。
副業に関係なく、これは当然のルールです。
普段から経済や時事ニュースを
よく見る公務員の方にとっては、
株式投資や投資信託は
取り組みやすい副業と言えるかもしれません。
公務員にもできる副業3:太陽光発電投資
「設置すれば放っておける」
そんなメリットがあるのが、太陽光発電投資です。
屋根や土地にソーラーパネルを設置して、
電気をつくって売ることで収入が得られます。
家庭用(10キロワット未満)なら、許可なしでOK。
たとえば自宅の屋根に設置して、
余った電力を売るようなスタイルですね。
ただし、産業用(10キロワット以上)の場合は、
事前に許可が必要です。
その場合は、設備の大きさや場所、
年間の収益見込みなどを提出する必要があります。
太陽光投資は、安く土地を買ってパネルを置いたり、
中古物件に設置したりと、工夫次第で広がります。
発電量の予測も立てやすいので、
リスク管理がしやすいのも魅力です。
公務員にもできる副業4: 講演や執筆などの活動
公務員がこれまでの仕事で身につけた
知識や経験を活かしてできる
代表的な副業が「講演」や「執筆」です。
たとえば、
こんな活動があります。
・専門分野について話す講演会
・本や雑誌に文章を書く
・新聞やウェブにコラムを寄稿する
・メディアのインタビューを受ける
・テレビやラジオに出演する
実際に、公務での経験や
立場から声がかかることもよくあります。
たとえば、「公務員試験ジャーナル」や
「月刊ガバナンス」といった雑誌に記事を書いて、
原稿料を受け取っている方もいます。
こうした活動を行うときには、
以下の点に注意が必要です。
① 守らないといけない「公務員の秘密」
まず一番大事なことは、
仕事の中で知った秘密を外に出さないことです。
たとえ講演や執筆であっても、
公務で知った内容を話したり
書いたりするのはNGです。
これは法律で決まっています。
絶対に守らないといけないルールです。
② 単発か?継続か?
講演や執筆が「1回だけのもの」なのか、
それとも「何度も続けて行うのか」によって、
必要な手続きが変わります。
人事院の例では、こう書かれています。
「1回だけ講演して講演料をもらった場合」や
「研究成果を1回だけ雑誌に書いて報酬を得た場合」は
公務員の副業ルール(国家公務員法104条)に当てはまらない
つまり、単発の活動は許可が不要。
継続的な活動は許可が必要になるということです。
だから、まずは単発から始めるのがおすすめです。
講演や記事執筆を一度やってみて、
続ける場合はルールを確認しましょう。
もし文章を書くのが好きなら、
小説の新人賞などに作品を応募することも可能です。
こういった懸賞金タイプの賞金、
「副業」ではなく「賞」なので受け取ることができます。
たとえば、新人賞で
100万円をもらうこともOKです。
ただし、賞をきっかけに連載が始まったり、
印税が入ってくるような継続収入になった場合は、
勤務先に確認や申請が必要になるので注意しましょう。
公務員にもできる副業5: 小規模な農業
農業も、公務員が
取り組みやすい副業のひとつです。
なかでも「自分や家族のため」に行う
小さな規模の農業なら、
基本的にOKとされています。
たとえば、家庭菜園のようなレベルで
野菜や果物を育てるくらいなら、問題はありません。
ただし、育てたものを出荷したり販売する場合は、
「仕事」とみなされるので、
事前に兼業許可が必要になります。
農業の規模が大きくなると、
副業と見なされる可能性が出てきます。
その判断は、自治体や職場によって少し違いますが、
一般的には、次のようなポイントを見て判断されます。
・耕している土地の広さ
・農業での年間の収入
・農作業に使う時間
・手伝ってくれる人(雇用者)がいるかどうか
特に、農業がさかんな地域では、
公務員が農業をすることも珍しくありません。
実際に、ある程度広い農地を持っていたり
収穫量が多くても、許可が下りるケースがあります。
不安な場合は、事前に
所属している部署に相談しておくと安心です。
公務員にもできる副業6.:社会貢献活動
社会に貢献する活動も、
公務員が取り組める副業のひとつです。
たとえば、こんな活動が
許可されやすい例としてあります。
・地域の少年スポーツチームのコーチ
・子どもへの学習支援ボランティア
・健康づくりのセミナー講師
・音楽や文化活動の指導
これらの活動は、社会的に意味があり、
善意にもとづいた活動だからです。
また、政治的なかたよりや
利益のための活動ではないため、
公務員としての中立性や
公平さが守られると考えられています。
長野県では、
「地域に飛び出せ!
社会貢献職員応援制度」という取り組みがあります。
この制度では、職員が部活動の指導や
日本語教室の講師などを
有償で行うことが認められています。
佐賀県でも、
ある公務員が「○○な障がい者の会」
という団体を立ち上げました。
この団体では、障がいのある方との
交流イベントなどを実施し、
共に生きる社会づくり(共生社会)に貢献しています。
公務員にもできる副業7: 不用品販売
家の中にある、いらなくなった物を売る。
この「不用品販売」も、
公務員が取り組める副業のひとつです。
たとえば、
メルカリやヤフオクなどのフリマアプリ、
オークションサイトを使って販売する方法があります。
こうした不用品の販売は、
お金をもうけることが目的でなければ
基本的には問題ありません。
ただし、公務員という立場では
モラルやルールを守る意識がとても大切です。
実際に、フリマサイトの使い方を間違えて
厳しい処分を受けた事例もあります。
【事例①】授業で使う教科書を売って処分
東京都立高校の40代の先生が、
フリマアプリで授業用の教科書9冊を販売し、
約1万1,500円の利益を得ました。
ところが、フリマの送り状を机に置きっぱなしにしていたことで、
他の先生に見つかり発覚。
この先生は、懲戒免職(=クビ)になったのです。
【事例②】仕事で使う道具を売って処分
東京都内の消防署に勤める40代の職員が、
職場から渡されていたヘルメットなどをフリマで販売し、
約36万円の利益を得ていました。
出品されていたヘルメットを消防庁が見つけ、調査を実施。
その結果、事実が発覚し
この職員も懲戒免職となりました。
これらのケースは、明らかにルール違反です。
仕事で使う物や、
支給された物を勝手に売るのはNGです。
一方で、自宅にある私物を
処分する範囲であれば問題ありません。
ただし、どこまでがOKかは
自治体によって違うこともあります。
不安なときは、事前に職場へ確認することが大切です。
公務員にもできる副業8: ポイ活
ポイ活というのは、
いろんなポイントサイトを使ってポイントをため、
それを現金やギフト券などに交換する活動のことです。
このポイ活は、節約や貯金にもつながりますし、
特別なスキルや知識がなくても始められます。
そのため、副業に慣れていない公務員にとっても
取り組みやすい副業のひとつといえるでしょう。
しかも、ポイ活は「働いた報酬」として
お金をもらうものではないので、
公務員でも問題なく取り組むことができます。
スマホひとつあればすぐに始められる。
この手軽さもポイ活の大きな魅力です。
でも、公務員として
守らなければいけない大切なルールがあります。
それは、
勤務時間中に絶対にやらないこと。
当たり前のことに聞こえるかもしれませんが
スマホでサクッとできるぶん、
ついやってしまいがちです。
実際に、こんな事例もあります。
2021年3月。大阪市の職員が、
勤務時間中にポイ活をしていたことが発覚。
その結果、停職3か月という厳しい処分を受けました。
この行為は、
本業である公務をおろそかにした、明らかな違反です。
公務員として、絶対に避けなければなりません。
ポイ活は気軽にできるからこそ、
「ちょっとだけ…」と、
勤務中にスマホを見たくなるかもしれません。
でも、あくまで
プライベートの時間だけにしておきましょう。
ここまで、公務員でもできる副業を
8つご紹介してきました。
中には「バレなければ何をやってもいいんじゃない?」と、
そんな気持ちになる人もいるかもしれません。
ですが、過去には許可を取らずに
副業をして処分を受けたケースもあります。
【事例①】
大分市役所の19歳の女性職員が、
水商売のアルバイトをしていたことが発覚。
その結果、2ヶ月間、
給料の1割が減額される処分を受けました。
この職員の手取りは、
月に10万円もありませんでした。
それでも、給料の半分以上を親に仕送りし、
生活費を補うために副業をしていたといいます。
【事例②】
大阪市の職員が、子どもの受験費用を稼ぐために
週に4〜5日、パチンコ店の清掃員として勤務。
1年間で約40万円を稼ぎましたが、
発覚後、3ヶ月の停職処分となりました。
このように、どんな理由があったとしても
許可のない副業は、処分の対象になります。
「バレなければ大丈夫」なんて軽い気持ちで始めると、
将来、大きな代償を払うことになりかねません。
公務員として副業をするのであれば、
必ず許可を取り、ルールの中で行いましょう。
次は、「公務員が絶対にやってはいけない副業」
についてお話しします。
絶対にやってはいけない副業1: ブログ・アフィリエイト
「特別なスキルがなくても始められる」
「自宅でコツコツ続けられる」
こうした理由から、ブログで
アフィリエイト収入を得たいと考える公務員の方もいます。
たしかに気軽にはじめられます。
ですが、公務員の副業としてはおすすめできません。
理由があります。
2021年10月、東京都が
ブログアフィリエイトを禁止する通達を出しました。
アフィリエイトの収入は、
何度も繰り返し発生します。
この仕組みが、営利目的の
「自営業」と同じと判断されたのです。
たとえば、趣味で
ブログやSNSをやるだけなら問題ありません。
でも、お金を得る目的でやると、
副業と見なされます。
では、ブログに代わる副業を
考えている人はどうすればいいのでしょうか。
その場合は、講演や執筆のような活動が向いています。
たとえば、原稿を書いたり、
記事を寄稿するなどの仕事です。
これなら、単発で終わるので、
公務員としても取り組みやすいです。
大切なのは、
ルールを知ったうえで正しく副業を行うことです。
絶対にやってはいけない副業2: 講座講師業
講演や社会貢献活動は、
公務員でも許可が出ることがあります。
でも、講座講師業は違います。
これは、NGです。
なぜかというと、
自分で講座を開いて料金を決めて人を集める。
このやり方が「自営業」と全く同じだからです。
こちらをご覧ください。

人事院のハンドブックにも、
こう書かれています。
「コーチング業を行った職員を減給処分にした」
つまり、営利目的で継続的に行えば、
処分の対象になるということです。
ただし、例外もあります。
たとえば、企業や学校から依頼を受けて、
一度だけ講師として登壇する。
このような形であれば、問題ありません。
ポイントは、自分から始めた活動かどうか。
それと、継続しているかどうかです。
迷ったときは、必ず事前に確認しましょう。
絶対にやってはいけない副業3: せどり
「せどり」とは、安く商品を仕入れて、
高く売ることで利益を得るビジネスのことです。
このスタイルは、
典型的な自営業と見なされます。
そのため、公務員が行うことは
原則として認められていません。
前にご紹介した「不用品販売」は、
条件付きで認められるケースもあります。
では、せどりとの違いはどこにあるのでしょうか。
ポイントは「目的」にあります。
不用品販売は、
家にある使わなくなった物を
一度だけ売るようなイメージです。
継続的な収入にはなりません。
一方、せどりは
最初から利益を出すことを目的に、
商品を仕入れて売るというビジネスです。
売って、また仕入れて、また売る。
このように、
繰り返し利益を出す行為は「商売」にあたります。
つまり、明らかな営利活動になるため、
公務員の副業としては認められないのです。
せどりに限らず、物を仕入れて売るビジネス全般は、
公務員に向いていない
と考えたほうがいいでしょう。
仮に、兼業の申請をしたとしても、
許可が下りる可能性は非常に低いといえます。
公務員が副業をする上での注意点
ここからは、公務員が副業をする際に気をつけたい、
大事なポイントをお伝えします。
副業をする上での注意点1:必ず事前に許可を取る
副業を始める前に、
所属している職場に申請を出す必要があります。
「少しだけならバレないだろう」
「お金もたいしてもらってないし」
そう思うかもしれませんが、
これは非常に危険です。
たとえば、自営業や
不動産賃貸を行う場合は「自営兼業承認申請書」。
会社や団体に雇われる場合は「兼業許可申請書」。
それぞれの手続きを、きちんと行っておくこと。
これは、自分のキャリアを守るためにも大切です。
副業をする上での注意点2:収入を家族名義にしない
副業収入を隠すために、
お金の受け取りを家族の名前にする。
これは絶対にやってはいけません。
発覚すれば、脱法行為とみなされ、
厳しい処分を受ける恐れがあります。
場合によっては、
信用もキャリアも失う結果につながります。
中には、こういった行為を「裏技」として紹介する人もいます。
たとえば、家族名義で法人を立ち上げて、
その法人から間接的に収入を得るという方法です。
この方法は、理論上は可能とされています。
たとえば、本人は法人の役員に名前を出さず、
表向きはボランティアとして関わるという形です。
ただし、
この方法も軽く考えてはいけません。
法人をつくるには、
10万円〜25万円ほどの設立費用がかかります。
さらに、税理士に依頼する
決算処理や法人税の支払いも必要です。
維持費だけでも
最低7万円ほどかかるといわれています。
そもそも、その副業が
法人化するほどの規模なのか。
長く続けられるのか。
これはケースによって大きく異なります。
自己判断で進めず、必ず税理士や行政書士といった
専門家に相談してから動くようにしましょう。
目先の利益ではなく、長い目で見て、
本当に必要な選択かどうかを見極めることが大切です。
副業をする上での注意点3:本業の名前を出さない
副業の場で、自分がどこの職場にいるのか、
それをアピールするのはNGです。
たとえば「〇〇省の職員が教える」
「〇〇市役所勤務の私が解説します」
こういった紹介の仕方はしてはいけません。
たとえ報酬が発生していなくても、
職場の名前を使う場合は、
必ず事前に確認が必要です。
副業をする上での注意点4:確定申告を忘れない
副業で得た収入は、
ちゃんと申告しないといけません。
一般的には、給与以外の所得が
年間20万円を超えたら、確定申告が必要です。
もし申告しなかった場合は、追徴課税だけでなく、
悪質とみなされれば脱税として処罰されることもあります。
副業の収入は、
雑所得や事業所得として申告するのが一般的です。
また、住民税の納め方にも注意が必要です。
たとえば、
職場で住民税を天引きされている場合。
副業の収入があると、
住民税が増えたことから職場に知られることがあります。
これを避けたい場合は、
住民税の「普通徴収」を選ぶことで、
自分で納めることができます。
いずれにせよ、収入があるなら必ず申告を。
これは、副業をするうえでの最低限のルールです。
まとめ
今回は、公務員の副業について
お伝えしてきました。
最後にポイントを振り返っておきましょう。
1つ目は、公務員の副業は「禁止」ではないということです。
条件を守れば、できる副業もあります。
憲法で認められている
「職業選択の自由」は、公務員にもあります。
ただし、公共の福祉を損なわないことが前提です。
そして、必要に応じて、
職場の許可をきちんと得る必要があります。
2つ目は、公務員でもできる副業は
たくさんあるということです。
たとえば、不動産投資、株式や投資信託、太陽光発電など。
こうした副業は、条件を守れば取り組むことができます。
まずは、お金をかけずにできる
簡単な副業から始めてみるのがおすすめです。
そこから少しずつ、
収入アップを目指していきましょう。
3つ目は、注意が必要な副業もあるということです。
ブログアフィリエイトや講座講師業、せどりなどは、
「くり返し利益を得ること」を目的としたビジネスです。
こうした活動は、自営業とみなされるため、
原則として認められません。
「少しだけならバレないだろう」という甘い考えは、
思わぬトラブルの元です。
4つ目は、副業をするうえで
守るべき4つのルールです。
ルール1:必ず事前に許可を取ること。
ルール2:収入を家族名義にしないこと。
ルール3:公務員としての肩書きを使わないこと。
ルール4:確定申告をきちんと行うこと。
副業は、ただお金を稼ぐ手段ではありません。
スキルや人とのつながりを広げる、
成長のチャンスでもあります。
ルールを守りながら、本業と両立できる副業を見つけて、
あなたらしくチャレンジしてみてください。
この記事を動画で見るにはこちら:

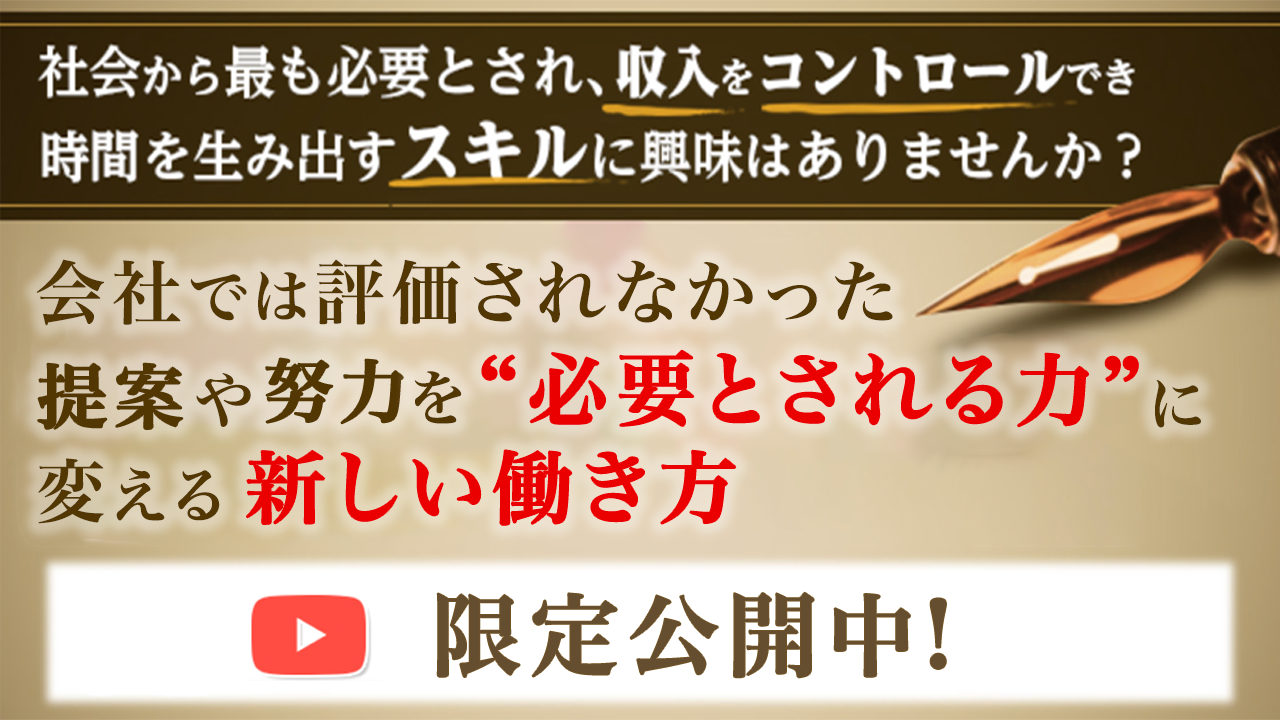

SNSアカウント